top of page
その他の研究
光学計測による後燃えの現象解明及び急速燃焼コンセプトの創出
SIPディーゼル燃焼チームの主な目的は2つあります.図1左にあるように街乗常用域である中低負荷領域のCO2排出量30%低減及び最大効率域である高負荷領域における最大熱効率を50%へ引き上げることです.
この2つの目標を達成するためにSIPディーゼル燃焼チームでは5つのグループ(図1中央)に分かれて研究を行っています.グループ2,3は高負荷領域での熱効率50%を,グループ4,5では中低負荷でのCO2排出量30%低減を担当し,グループ1がそれらを統括,という形で動いています.
それでは熱効率をどのようにして50%へ到達させるのか?
図1右は,投入された燃料を燃やすことで得られた熱エネルギーがどのように消費されているのかを示す熱バランスです.従来のエンジンでは実に半分以上のエネルギーが損失として捨てられています.これら損失を大きく3つに大別(排気損失,冷却損失,摩擦損失)しそれぞれの損失メカニズムを明らかにし低減することでトータルとして熱効率50%を目指します.
グループ2では明治大学相澤研がグループ長を務め,この排気損失低減を目標に6大学で連携して取り組んでいます.

図1. SIPディーゼル燃焼チームの研究背景
排気損失とは何か?
内燃機関ではピストンによって圧縮された空間で燃料を燃やし,ピストンを押し下げる仕事をさせることでエネルギーを取り出しています.上死点(ピストンが一番上まできて圧縮している点)で全ての燃料を燃やし,膨張することで燃焼ガスが十分に冷えた状態で筒外へ排気できれば熱エネルギーを効率よく取り出せたということになります.しかし,近年のディーゼルエンジンでは街乗常用域である中低負荷のエミッション改善のために小噴孔径燃料噴射装置を採用する傾向にあり,パワーの必要な高負荷領域において噴射・燃焼期間が相対的に長くなってしまっています.燃焼期間が長くなることで膨張行程においてもダラダラと熱エネルギーを放出し続け,結果的に排気温度が上がり,エネルギーを効率よく取り出せなくなってしまいます.この後半部分の燃焼を"後燃え"と呼びます.
グループ2ではこの後燃えを低減し,等容度を現状の0.9から0.98まで引き上げることで熱効率向上を目指します.
後燃え低減のためにはまず,後燃え現象がエンジン筒内の「どこで」「何によって」「どの程度」律速されているのかを明らかにしなくてはなりません.相澤研ではこれらの情報をエンジン筒内で可視化する手法の確立を手がけています.具体的には,エンジン筒内の温度・圧力条件を模擬した容器内で熱発生や燃料分子の可視化実験を行い,結果を評価するというものです.
相澤研で確立された手法をグループ内で共有し,多気筒エンジンに応用(千葉大)したり,定量的な燃料分子などの化学種濃度を評価(徳島大),シミュレーション結果と比較(早稲田大),後燃えにおけるPM生成・酸化メカニズム調査(東京大,日本大),を行うことで後燃え現象を解明し,その低減方策を現実的なハードウェアを用いて実現していきます.

図2. グループ2 後燃え低減へ向けての研究の進め方
図3は相澤研で確立したディーゼル燃焼中の熱発生領域可視化手法の例です.燃焼中間生成化学種であるOH*は特定の波長(310 nm)の光を自ら放出します.この化学種は燃焼の始まる位置を定義するLift-off(厳密にはSet-off)として広く知られており,熱発生とも深い関わりがあると考えられています.このOH*自発光を高速度カメラで撮影することでエンジン筒内熱発生領域の可視化が可能となると考えられています.
すす粒子から放出される輻射光にも310 nm付近の紫外線が含まれているため,これらの領域と区別するためにすす粒子の輻射光とOH*自発光を同時に撮影しています.

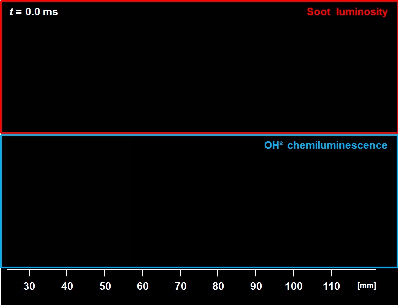
図3. 輝炎及び紫外自発光の同時時系列撮影光学系とその動画
bottom of page